年長夏スタートで4ヶ月!超短期集中で難関校に合格したけれど…
わが家が難関私立小学校受験を決意したのは、年長の7月。
そこから約4ヶ月間で急ピッチの準備を進め、最難関私立小・超高倍率国立小と、受験したすべての学校に合格することができました。
…とはいえ、正直かなり過酷なスケジュールだったのは事実です。
娘・キララちゃんは「1を言えば10理解するタイプ」で、集中力・素直さなど生まれ持った性質に恵まれてなんとか乗り切れましたが、このやり方は再現性が低いと感じています。
そして、たった4か月で難関校の合格をつかむことは、振り返ってみてもかなりハードでした。
その頃の私たちは時間に追われていて余裕もなく、親の私も心身ともにボロボロでした。
「もし時間を巻き戻せるなら?」今ならこう進める理想スケジュール
下の子が同じように受験を目指すとしたら、私はもっと早く・丁寧に準備を進めていきます。
その経験から逆算して導き出した「理想の受験準備スケジュール」をご紹介します。
【年中以前】受験を意識する前にできる“日常の土台づくり”
「小学校受験を始めたのは年長の夏」でしたが、振り返ってみるともっと前からできることがたくさんあったと、今は痛感しています。
👇 こちらの記事でも紹介している「受験準備前の日常習慣」も鍵だったと考えています。
● 読書習慣を自然に取り入れる
毎日の絵本タイムを、親子の会話と気づきの場に。
● 自立心を育てる声かけ
「自分でやってみよう」「どうしたらいいと思う?」といった一言が、思考力や判断力の第一歩に。
● 観察力や好奇心を伸ばす遊び
積み木・ブロック・外遊びなどは“考える力”の宝庫。問いかけ次第で学びに変わります。
● 学習の習慣化
登園前に毎日スマイルゼミを取り入れており、「学習が生活の一部」になっていました。
【反省点1】志望校を早く決めて、過去問はもっと早く買うべきだっ
これは、わが家にとって一番の反省点です。
志望校を難関私立とすることに決めたのは年長の7月でしたが、もっと早い段階で志望校を決め、過去問を購入し、出題傾向を親がしっかり把握しておけばよかったと思います。
▼ こんな工夫ができたはず
- 「昔話の比較」が頻出なら → 読み聞かせ中に「この話、似たようなのあったね?」と会話に取り入れる
- 「動物の足跡」が出るなら → 普段から動物の足を見て「どんな足跡だろうね?どんな歩き方かな?」と問いかける
- 「数の操作」がよく出るなら→お菓子を食べるときにも「パパとママとキララちゃんと弟くんの4人で分けたらひとり何個ずつ食べれて、何個余るかな?」などと実際に体験してみる
\日常生活に“頻出テーマ”をなじませる/
これができていれば、短期でももっとスムーズに対策が進んだはずです。
【反省点2】絵本の読み聞かせに“受験視点”を取り入れればよかった
読み聞かせは日常的にしていたのですが、あと一歩「受験的な視点」を加えられていたらもっと良かったと感じています。
▼ 具体例
- 『ぶんぶくちゃがま』→「たぬきが出てくるお話、他にもある?」→「カチカチ山!」
- 『おやゆびひめ』→「小さい人といえば?」→「一寸法師!」「かぐや姫も小さい頃は…」
こんな風に物語を比較したり、共通点を見つけたりするような会話が、「比較・連想・思考力」の土台となり、「考える力」も養えます。
【反省点3】積み木遊びは“空間認識トレーニング”にもなる
積み木で遊んではいたものの、もっと観察力や推測力を育てる遊び方ができれば、図形感覚を楽しく育てられたかもしれません。
▼ 声かけの例
- 「この形、上(下・反対側・横)から見たらどうなる?」
- 「いくつの積み木でできていると思う?」→ 予想して答えた後に崩して検証!
積み木は、図形問題の土台をつくる最強の教材です。
【反省点4】季節行事・文化的背景・植物の知識を深めておけばよかった
保育園でも季節行事はありましたが、家庭でもう少し深掘り・補足できたと思います。
▼ 深堀りできた例
- 「今日は十五夜だね。月見団子ってどんな意味があるんだろう?」
- 「一升餅・鏡餅・菱餅・柏餅…どんな行事と関係があるの?」「今日は端午の節句だね。お餅を買いに行くけど、端午の節句には何のお餅を用意するかな?一緒に買いに行こう」
- 咲いているお花を見て「これは〇〇だね。春に咲くお花だね」
お花屋さんに行って「せっかくだから、今の時期に綺麗なお花をキララちゃんが選んでくれる?」
文化的な背景を一緒に調べて知ることは、「一般常識」「言語理解力」の強化につながります。
【年中秋〜新年長】本格的な受験対策スタートはこの時期が理想!
わが家の経験を踏まえると、本格的な幼児教室やペーパー演習の開始は新年長となる年中秋がベストタイミングだと考えます。
先述したように、受験のベースとなる知識を楽しみながら会得できていれば、基礎が自然と身についている状態で、そこからさらに
- 知識の定着
- 行動観察・面接対策
- スケジュール管理
など、バランスよく進められます。
そのような基礎を身につけさせる時間と自信がなければ新年長以前から幼児教室に通うことも検討するかもしれません。しかし、幼児教室が仮に週2時間だとしたら、家庭で過ごす時間が睡眠など生活を除いて週20時間だとすれば、10倍以上あることになります。その中で楽しみながら学ぶ方が効率的だと私は考えます。
Q:受験まで1年で間に合う?
→ A:親の“伴走力”がカギ!
1年あれば合格レベルまで仕上げることは可能ですが、成功のカギはやはり「親の伴走力」にあります。
▼ 大切なのは…
- 毎日の理解チェック
- 苦手の早期フォロー
- 子どもと一緒に考える柔軟な姿勢
\短期集中より“継続と寄り添い”が再現性高め/
子どもにとっても、負担が少なく着実に力を伸ばせます。
まとめ|一番の準備は「家庭での愛情ある学び」
最後に。
わが家が4ヶ月の短期受験を乗り越えられたのは、娘が「愛されている」という確かな実感を持っていたからだと思います。
自信や行動力、他者を思いやる心。
それは受験にも、そしてその先の人生にも必要な“生きる力”です。
今でも娘とこう話しています。
「本当に大変だったけど、あのとき一緒に頑張ってよかったね」
「一緒に過ごした時間は、今でも宝物だね」
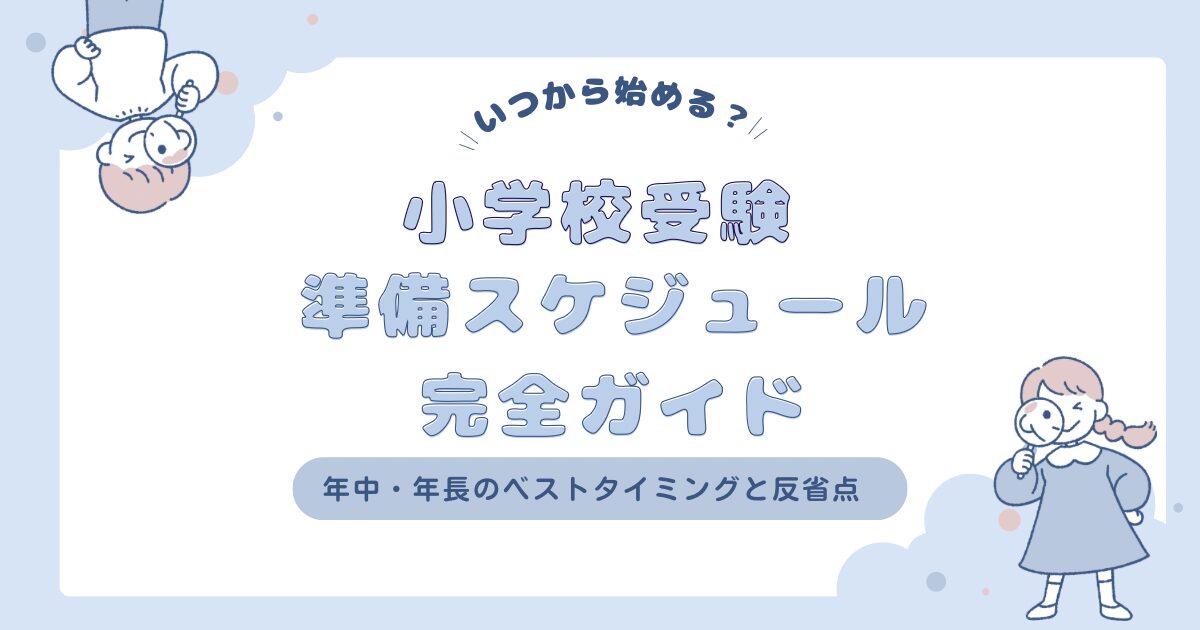




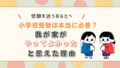
コメント